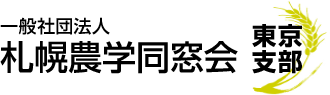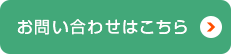札幌農学同窓会東京支部2025年度総会及び講演会 開催報告
2025年2月15日(土)に札幌農学同窓会東京支部2025年度通常総会を開催し、事業報告、事業計画、役員交代などについて審議いたしました。また、総会に引き続き、北海道大学大学院農学研究院から小出陽平准教授を講師にお招きし、講演会を開催いたしました。
【通常総会の概要】
2025年度通常総会においては、以下の議案が審議され、いずれも承認されました。
- 2024年度の事業報告及び決算報告
- 2025年度の事業計画案及び予算案
- 2025年度役員体制案
なお、今年度の事業計画では、新規企画として6月に新会員歓迎を開催することの紹介がありました。また、理事長、副理事長の交代など役員の大幅な入れ替えが行われる節目の総会となり、新体制で今後の活動を進めていくことが確認されました。
【講演会の概要】
北海道大学大学院農学研究院准教授(植物育種学研究室)小出陽平先生を講師としてお招きし、「リジェネラティブ農業システムの構築と新たな作物開発への挑戦」との演題、母校北大が現在注力している「地域中核・特色ある研究大学強化促進事業(J-PEAKS)」の取組の紹介とそれに関連する小出先生自身の研究についてお話しいただきました。
以下、講演概要です。
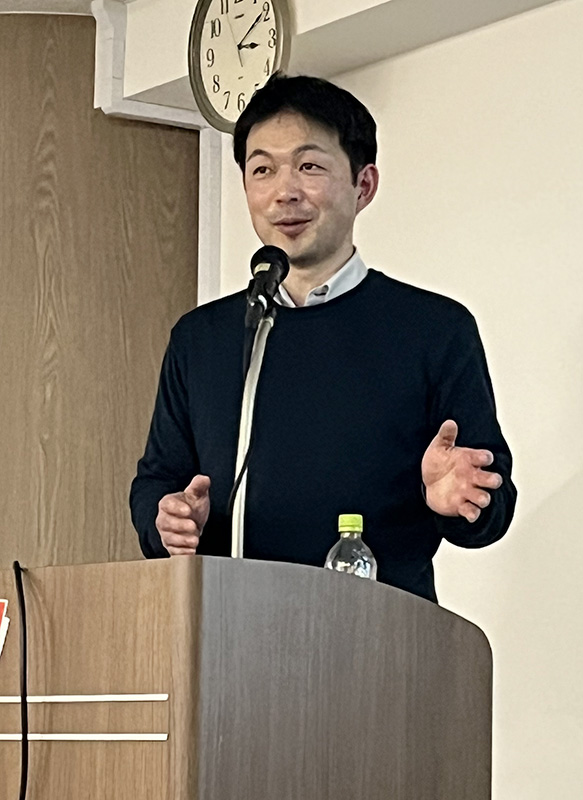
1.地域中核・特色ある研究大学強化促進事業(J-PEAKS)
J-PEAKSは、地域の中核大学や特定分野の強みを持つ研究大学に対して、多様な機能を強化し、日本の成長の駆動力へと転換させる、「地域中核・特色ある研究大学総合振興パッケージ」の下で実施される事業であり、北海道大学は、第一期の支援対象12大学のひとつに選ばれ、取組が開始されています。この事業は、大学の取り組み強化、他機関との連携強化、地域社会での活動促進を目的としており、北大は「フィールドサイエンスを基盤とした地球環境を再生する新たな持続的食料生産システムの構築と展開」というテーマで選ばれています。支援額は約50億円で5年間継続し、進捗に応じて最長10年を目途に延長される可能性があります。
2.J-PEAKSにおける北大の取組
(1)リジェネラティブ農業について
北大では、J-PEAKSでの取組において、研究卓越力と社会展開力を縦軸・横軸とした持続可能性の追求によって地域・世界の課題解決を図ることを目指しています。そのため、総長直轄の推進組織の設置や研究連携などの機能強化、DX化といった推進基盤の整備を進めつつ、リジェネラティブな持続的食料生産システムの研究に取り組んでいます。この枠組みの下、農業、水産業、フィールド科学の分野で新たな研究が進められておりますが、その中心となる農学部においては、リジェネラティブ農業(環境再生型農業)の推進を担当しています。
リジェネラティブ農業とは、プラネタリー・バウンダリー(地球の限界)を考慮し、環境への負荷を減らしながら持続可能な食料生産を目指すものです。現在の農業システムは、化学肥料や農薬の過剰使用などにより物質循環から逸脱し、生物の多様性と共生が喪失されるなど様々な問題を抱えており、その解決に向けて、リジェネラティブ農業の研究では、低投入・高収量・低排出を実現し、自然環境や地域の風土に適した食料生産システムの構築を目指していきます。

(2)北大農学部における取組事例
農学研究とは何か、その広がり、ビジョンを突き詰めて考えると、農業の複雑な生態系を理解し、革新的な農法技術を開発し、それらを地域や市場経済に波及させる、という3つの柱に収斂されます。そのような考え方の下、この研究計画では、生態系サービスを最大限生かし、その多様性を破壊しない食料生産法を確立するとともに、AIやIoT技術を活用して環境再生型農法の合理的設計を行い、それらの国内拠点での実証試験、そしてフィードバックを基にした技術改良などを行いながら、最終的には、環境再生型農業の普及と北大発のアグリテックの国際展開を目標にしています。現在、農学部には、野口研究院長をトップとした実施体制が組織され、自分もプロジェクトリーダーの一人として活動しています。
次に、農学部において持続的な食料生産システムに活用できる個別の研究がどのように進められているか、いくつかの事例を紹介します。
まず、AIやロボット技術を活用したスマート農業の研究が野口教授を中心に進められています。ロボット技術で大幅な省力化や夜間作業を可能にするなどの技術開発が進められています。また、ベトナムでのスマートカーボンファーミングのシステム構築を目指した研究が信濃教授の下で行われています。さらに、浅野教授を中心に、微生物の生産する殺虫性タンパク質と殺虫効果が期待できる害虫との組み合わせを超高速でスクリーニングし、生物農薬の開発につなげるシステムの開発や、近藤教授が進めるザンビアでの市民参加型品種改良プロジェクトなどもあります。
今ほど、具体的で分かりやすい研究目標を設定すべきだという意見をいただきましたが、これらの具体的研究で成果を出しながら、バランスを保ちつつ農業システム全体を最適化し変革していくことが重要と考えます。
3.新たな作物開発への挑戦
最後に、リジェネラティブ農業とも関連しますが、現在自分が進めている植物育種学に関する研究について紹介します。
植物育種研究室の源は、明峰正夫先生を初代教授とする日本で最初の作物育種の研究室です。育種の基本は、遺伝変異の拡大と収束にありますが、現在は、未利用資源を利用した遺伝変異の拡大と、収束させる技術として数理モデルを用いた品種改良技術の開発に取り組んでいます。
未利用資源としては、野生稲に着目しています。野生の稲から栽培稲への進化過程をみたとき、野生祖先種には、栽培種に導入可能な様々な有用遺伝子があると考えています。未利用遺伝資源を活用した雑種強勢と、雑種不稔克服技術で、新規有用品種の創出が可能となります。
他方、数理モデルを用いた植物の形態制御の研究を行っており、作物の成長や形態変化を数理モデルでシミュレートし、器官形成モデルを構築しようとしています。この数理モデル技術を活用すると、将来的には、長期間の繰り返しが必要な作物栽培試験をコンピューター内でシミュレートすることで、農業研究の大幅な効率化が期待できると考えています。

4.質疑応答
- Q:リジェネラティブという用語の定義について
- A:リジェネラティブについては、環境再生に向けた技術や思想を指すが、農法としての定義は未だ明確ではない。
- Q:リジェネラティブとサステナブルの違いについて
- A:リジェネラティブという言葉には、サステナブルに比べて、より積極的に環境を良くしていこうとする思想が含まれている。
- Q:数理モデルを用いた研究の将来性について
- A:数理モデルを用いた研究では、遺伝子の働きを物理的パラメータに落とし込むことで、品種改良の予測が可能になる。