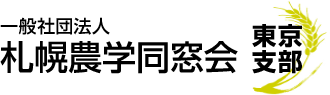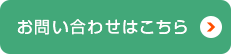札幌農学同窓会東京支部 夏の講演会(7/26) 開催報告
講演会の概要
2025年7月26日(土)に、別所智博氏を講師にお招きし、「令和の米騒動と食料安全保障」と題して講演会を開催しました。会場は昨年と同じミウラ・ドルフィンズ(渋谷区千駄ヶ谷)でした。
出席者は会場に20名、オンラインでは30名以上の方にご参加いただきました。
講師略歴
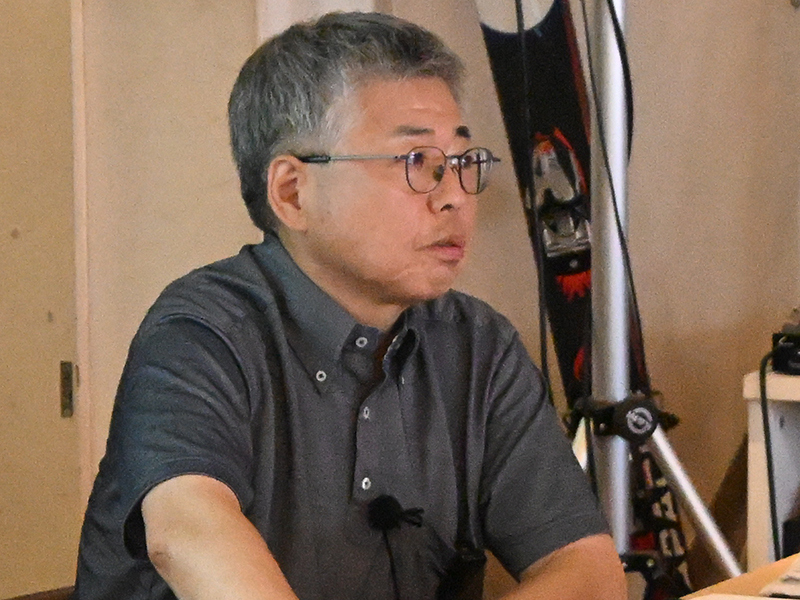
1981年、北海道大学農学部農芸化学科を卒業。
同年、農林水産省に入省。農林水産研究所長、大臣官房技術総括審議官などを歴任。
2019年、農林水産省を退職。
2025年、札幌同窓会東京支部理事長に就任。
講演の要旨
1.はじめに
札幌農学同窓会東京支部支部長の別所です。今回は、「令和の米騒動と食料安全保障」というテーマで、米騒動の要因を分析するとともに、食料安全保障の視点から今後の政策のあり方を考えていきたいと思います。
2.令和の米騒動とその要因
「令和の米騒動」は、令和6年の端境期におけるコメの品薄感に端を発した産地での買入価格と消費者価格の高騰と総括できます。価格高騰の大きな要因は、5年産米の民間在庫が、需給見通しよりも20万トン以上少ない153万トンと、過去最低の低水準となったことにあります。もともと6月末の民間在庫量が少ないと新米が値上がりする傾向がありましたが、今回は、南海トラフ地震臨時情報による買い込み需要によって一時的に店頭から米が消えたことの心理的影響も加わって、上昇幅がより大きくなったと考えられます。

また、民間在庫が需要見通しよりも少なくなったのは、需要が増加したためですが、その背景には、小麦の国際価格の高騰でパン・麺から米に需要がシフトしていたこと、5年産米の高温障害による品質低下で精米歩留まり率が低下したこと(結果として玄米ベースの需要量が大きくなったこと)などがあります。
このように5年産米の需給が逼迫したことから、産地では、JAや民間業者による6年産新米の買い入れ競争が激化し、価格が高騰しました。加えて、新規事業者の参入などにより、既存の主要ルートでの流通量が減少し、市場が品薄傾向で推移したことなどから、卸業者の高値での販売商品確保などの動きがあり、消費者価格は産地価格以上に高騰しました。
政府による備蓄米売却で供給量不足や低価格米需要への対応などに効果がありましたが、すでに高騰してした6年産の銘柄米の大幅な価格低下にまでには至っておらず、7年産米についてもJAや民間業者による買い入れ競争が予想されており、価格の先安感はありません。
3.食料自給率と食料安全保障
しかし、「令和の米騒動」は単に一時的な価格高騰の問題にとどまらず、今後の米政策や我が国の食料安全保障にもかかわる課題であり、需給見通しの精度、適正な価格水準や生産調整のあり方、長期的な生産力の確保など多くの政策的な論点を含んだ問題です。さらに議論を深めるために、いったん米騒動から離れ、食料自給率と食料安全保障について考えてみます。

食料自給率として最もポピュラーな指標が供給熱量ベースの総合自給率です。国民一人一日当たりの供給熱量に対する国産供給の割合ですが、現状は38%と、昭和40年の73%からほぼ半減しています。低下の主原因は、自給率100%の米の消費が半減し、自給率の低い畜産物や油脂の消費が増えたことにあり、食生活の変化が自給率に影響を与えます。また、戦時など供給熱量が低下すると、結果的に自給率が高くなるなど、単純にこの指標だけをもって食料安全保障を評価できるものではありません。また、我が国が輸入している農産物を面積に換算すると913万ヘクタールと日本の農地面積の2倍以上と試算されます。すなわち、「食料自給率100%」というのは、現実的な政策目標とはなり得ません。
食料安全保障とは多面的な概念であり、FAOの定めるFood Securityの定義を分解すると、供給、アクセス、利用、安定の4つの要素があるとされています。我が国の食料・農業・農村基本法も、昨年改正され、食料の安定供給に加えて、国民一人一人の食料安全保障という考え方が追加されるなど、より包括的な考え方になりました。その背景には、我が国の食料安全保障に関して、国内農業の脆弱化や農産物価格の低迷、食料アクセス困難人口の増大、国力としての食料輸入力の低下などさまざまなリスクが指摘されていることがあります。
食料安全保障の多面的な視点から令和の米騒動を見たとき、まず、短期的にせよ米の安定供給が損なわれたという問題があります。また、高騰以前の米価では、農家所得は、平均時給ベースで最低賃金以下になるということを踏まえると、長期的な米生産力の確保も課題となります。さらに、物価高が続く中で米への経済的アクセスが困難化しているという一人一人の食料安全保障の問題もあります。次にこれらを踏まえ、今後の米政策のあり方について考えてみます。
4.コメ政策の歴史と今後のあり方
最初に米政策の歴史を追ってみます。まず、米流通については、戦後、食糧管理制度による政府の全量管理が続きましたが、1995年の食糧管理法廃止で計画流通制度に移行し、民間流通が主体となりました。さらに2004年には完全に自由化されました。それに合わせて、生産調整についても、食管制度の下では、過剰米処理に要する財政負担の軽減を目的とした政府のための減反でしたが、食管制度の廃止以降は、民間流通する米の価格下落を防止することが主目的になりました。さらに2015年には目標配分も廃止され、現在は、政府の公表する需給見通しと補助制度の下でJAなどが自主的な調整を行うというものになりました。
このように、米については、流通が自由化され価格も市場が決める普通の商品となりました。他方、依然として米農業は国内農業の中心であり、基礎的食料である米については、政府が備蓄を運営し、生産調整に関与するとともに、輸入も国家管理しています。このように米は、経済的商品と基礎的食料という一見対立しそうな2つの側面を有しており、そのバランスをどう取るかがこれからの政策を考える上で、重要となります。
ところで、我が国の水田面積は約220万ヘクタールであり、全面的に主食用米を作ると約1100万トンと、現在の主食用米需要量約700万トンを大きく上回ります。水田を食料生産の重要資源として、全面的に有効利用していこうとすると、麦・大豆などの畑作物生産や飼料用・加工用など主食用以外の用途の米生産にある程度振り向けていく必要があります。
今回の米騒動に関連して、生産調整を廃止すべきとの指摘がありますが、廃止するのであれば、この水田資源の配分が予定調和的に行われ、需給や価格が混乱しないということが見通されるか、あるいは混乱しても生産から消費に至る食料システムが健全に維持される政策を用意しておくことが必要です。
また、生産調整の有無にかかわらず、天候・社会要因で需給ギャップは大なり小なり発生しますので、いずれにしても、需給と価格の変動に対する政策を用意する必要があるともいえます。供給不足・価格高騰に対しては、代替財の確保とアクセス困難者に対する支援が必要ですし、供給過剰・価格下落に対しては、生産者の経営継続のための支援や過剰処理対策が必要となります。
さらに、米の生産が長期に持続的であるためには、生産コストに見合った価格により生産者の所得が適切に確保されることが必要になります。その方法としては、価格下落時に補填金や保険金でカバーするセーフティネットのようなタイプの政策と価格変動とは無関係に生産者に一定の直接支払いを行うタイプの政策(いわゆるデカップリング政策)が想定されます。
当然、その際には、財政の効率化を考えなければなりませんので、セーフティネットにしろ、直接支払いにしろ、生産者全員を政策対象にするのか、対象者に要件をかけて規模拡大や法人化などの政策誘導を行うかなども論点になります。
5.まとめ
最後にまとめます。今回の米騒動の反省を踏まえれば、供給不足に対する代替財の確保という点で準備不足だったと考えます。備蓄の量と機動性を見直すのか、他用途米の転換なのか、輸入米なのか考え方は、対応手法は多様ですが、「需給と価格の安定は政府の役割」という法律上の考え方をもとに、もっと懐の深い需給調整を行える政策を整備する必要があると思います。また、生産調整については、水田資源のすべてを主食用米生産に向けることはできないという現実を踏まえて、需給見通しの公表、助成制度など、政府としてどのような強度で関与したらよいのか考える必要があります。そして米生産を持続的にしていくためには、生産コストを反映した合理的な価格形成が行われることや価格変動に対して所得が守られるような政策が必要ということです。単に価格高騰の問題と捉えるのではなく、背景にある多様な政策課題にどのように対応すべきか考えさせたのが、今回の「令和の米騒動」であったということをお伝えして終わります。